967年5月、セニオリス共和国で施行された第5回選挙は、最終的に大統領選をミラ・イェリッチ候補が、議会選も人民戦線が141議席を獲得するという大勝を遂げた。
社会主義体制実現にむけ、憲法改正発議の条件は満たされた。
かつて「資本主義の擁護」を国是とした国は、実現不可能な議会平和革命を目前にしている。
「民主主義」はこの国をどこに向かわせるのだろうか・・・。
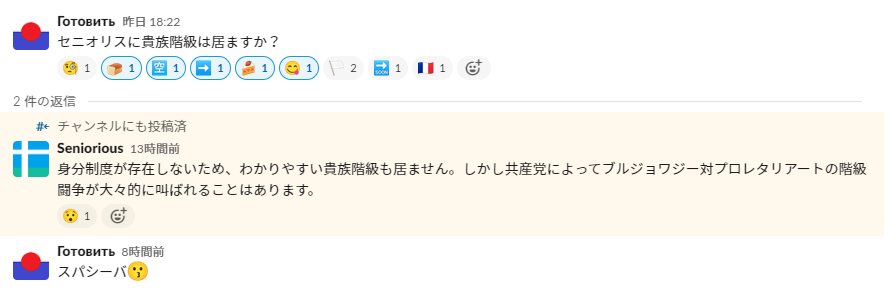
19世紀ヨーロッパの話をしよう。攻撃目標はヨーロッパだ!
政治→王侯貴族による支配が後退し、自由が肯定されるようになった。
経済→産業が飛躍的に発展して、富が急速に増大した。
・・・だが、それに伴って貧困や不健康や風紀紊乱が慢性化し始めた。
社会主義運動や社会主義思想が登場したのはこうした時期だった!
と言っても「まぁ、そりゃそうなんじゃね」と思うだろう。
社会に何らかの矛盾が発生していることは、誰の目にも明らかだった。
当時は、社会主義者だけではなく、多くの立場の知識人や有力者が、低賃金や過重労働や失業に起因する諸問題に対して危機感を募らせていた。
なぜかと言えば、その諸問題というのが、社会の存立そのものを脅かすほど、悪くなる一方だったからだ。
資本主義の先発国であるイギリスは、自動的に労働者問題の先発国にもなった。
実際、近代イギリスにおいて労働条件を規制する立法措置が取られたのは、早くも19世紀初頭のことだった。
具体的には、1802年の「徒弟法」制定がそれである。
さらに1819年には「紡績工場法」が制定された。
この2つは諸々あって実効性を欠く結果に終わってしまうのだが、それでも、この立法措置が先駆的なものであったことに違いはない。
ここで注意したいのは、これが「民主化や自由主義の成果ではない」ということである。
二つの先駆的立法は、新興のブルジョワジーが政治的な権力を強める前に行われたもので、自由主義の拡大に先立つ法律なのである。
もちろん、貧困を個人の自己責任に帰した新興ブルジョワジーにしても、現実問題として、労働者階級の困窮や荒廃を無視できる状況ではない。
当時は、為政者であれ、社会主義者であれ、自由主義者であれ、多くの立場の人々が、労働者階級の困窮や荒廃に伴う問題に危機感を抱かざるを得なかった。
軍隊も学校も教会も警察も、そして一部の資本家も、この危機感を共有していたのだった。
不健康で、不道徳で、無知な貧困層が溢れることは、単に生産性が悪化するであるとか、風紀が乱れるといったことだけでなく、伝染病蔓延の温床にすらなりはじめていたからである。
事実として、イギリスは1830年代から1840年代にかけて、コレラや腸チフス等の大流行に苦しめられている。
こうした社会問題が深刻さを増していく中で、ついに実効性のある労働規制が成立した!
それが1833年の「一般工場法」と呼ばれる法律である。
この立法に最も力を注いだのは、貴族のアシュレー卿であり、逆に、ブルジョワジーは一連の工場立法に一貫して強く抵抗していた。
プロレタリアートの窮状に目を向けたのは、多くの場合、旧来の支配層だった。
一般工場法では、16歳以下の夜間労働を禁止し、その労働時間を一日12時間に制限したのだが、これは国家権力による私的自由の制限に他ならない。
自由主義の原則に照らせば、どこで誰がどれだけ働こうが、全て当事者の自由なのであって、国家権力が介入すべき事柄ではないということになるだろう。
さて、未成年者の労働制限だけで、労働者階級の荒廃が解決するわけもなく、1842年には「鉱山法」で成人女性の地下労働が制限され、1847年の「工場法」では、ついに成人女性の労働時間が一日10時間に制限された。
この法律も、貴族などの保守勢力が、自由主義者達の抵抗を押し切って成立させたものだ。
少し話がそれるのだが、一連の立法では、まず子供が賃金労働から解放され、次いで女性が解放された。
つまりこれによって、成人男性だけは外で労働に就かざるを得ないが、女性と子供は家庭に留まるという様式が確立されたといえる。
そして、成人男性の労働時間を規制する法律は、19世紀を通じて一つたりとも成立しなかったのである。ぴえん。
御存知の通り、20世紀も後半になると、多くの先進国において、男女の性別的役割が固定化されていることが問題視されはじめ「女性の社会進出」が政治課題となった。
話をそらしても伝えたかったのは、現在の価値観で過去の歴史を意味づけてはならないわけであり、雇用機会における男女の区別は、かつては女性解放の成果だったということだ。
男性が女性を家庭に押し込めてきたとかいうのは、ブルジョワ富裕層に限った話であって、圧倒的大多数の庶民とは関係がない。
19世紀の産業化の時代にあって、庶民の女性や子供は、その意思にかかわらず、過酷な労働に従事なければ生きていけなかったのだから。
そしてもっとも哀れなのは、長らく解放される気配すらなかった成人男性だけなのであった。ぴえん。
フランスの思想家であるジャン・ボードリヤールは、「記号の経済学批判」の中で「資本主義システムは、何よりもまず女性と子供を可能性の限界内で働かせることをその本質としている」と指摘している。
純然たる資本主義は、平民と貴族を、キリスト教徒と異教徒を、自国民と外国人を、黒人も白人も黄色人種もスラヴ人も、女性も男性も大人も子供も、マジでまったく何ら区別しない。
「みんなみんな、生きているんだ、自由な個人なんだー」ということなのだ。
過去の社会主義の話でも述べたように、資本主義システムにとって、労働力は商品である。
だから、その商品を出来るだけ割安で買うことだけが重要であって、商品の売り手が誰であろうと、一切どうでもよいのである。
そもそも資本主義的生産様式は、利潤を最大化させること以外に関心も目的も存在しない。
資本主義システムに対して、それ以外のことを期待しても本質的に無駄だ。
これを逆から捉えると、資本主義の独走を抑制し得るのは、それとは別の系列に属する力でしかない。
極端な話、資本主義社会を内側から改革することなど不可能だということである。あくまで理屈上だが・・・。
経済的自由主義というのは、資本主義が独走できるように、障害を除去していこうという考えに他ならない。
ここまで述べてきたように、イギリスで工場立法を支えたのは、旧来の支配者層であって、資本主義の体現者達ではなかった。
ブルジョワジーの側は、小さな政府を求め、資本主義とは別系列に属する力を最小化しようとしていたのである。
しかしこういった疑問をもたないだろうか?
過去の歴史的事実に照らせば、資本主義を旨とする社会は、庶民層の生活水準や労働条件を大きく改善してきたように見えないか?
有り体に言えば、資本主義国のほうが、社会主義を掲げた国(これをあえて社会主義国と呼ぶことは避ける)よりも、労働者の生活は豊かじゃないか?
・・・しかし、この結果は資本主義自体の本質に起因するものではないということだ。
現実として、資本主義社会は利潤の最大化だけに向かって直進してきたわけではない。
資本主義社会には、資本主義的生産様式とは別系列の力として、大なり小なりの国家権力が存在していた。
「完全な形での社会主義が存在しない」ことと同じで「完全な形での資本主義が存在しない」のは、つまりそういうところにある。
資本主義は、何らかの形で国家の統制を受けてきた。おそらくこれは社会主義が存在しようがしまいが同じことだったろう。
純粋な形での資本主義も社会主義も存在せず、そこにあるのは混沌とした「バランス」にほかならないのである。
工場法は、新興ブルジョワジーの論理と、旧来の支配層の論理のバランスの中で成立したものであった。
労働力の売買について、その自由を制限しながら、成人男性の労働条件に関する規定を欠いていた理由はここにある。
19世紀後半から、福祉に関心が寄せられるようになったのもまた、利潤への関心とのバランスである。
それは政治的過程を経て、一人一票の基礎の元、資本主義とは別系列の有効な力として生まれてきたものなのである。

あなたのバランスはどこにあるのかな?
ヴェールヌイはセニオリスを凝視している。