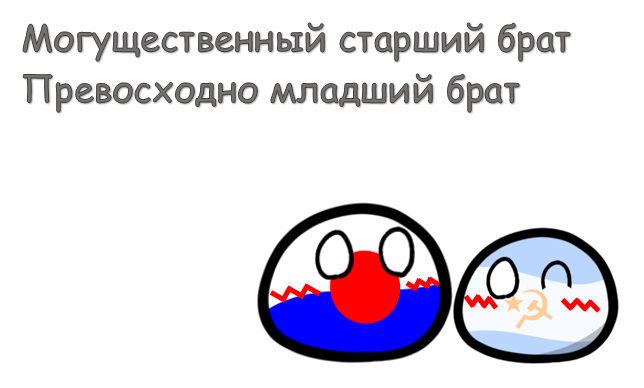※この記事はアンソロジーだが公式設定であり、そしてタイトル詐欺である

「ヴェールヌイとガトーヴィチは兄弟国である」このように表現されるようになって久しい。
政府や官公庁の発する文章、とりわけ外交文書において、ガトーヴィチを指し「兄弟」という語が登場したことは一度もないのだが、非公式協議の場や、人民議会外交委員会などでの一議員の発言として「同胞」「同胞国家」の表現は度々登場している。「同胞」は、ガトーヴィチに限って使用されているわけではなく、過去には「ヴォルネスク」「ベロガトーヴィチ」「ロシジュア」を指して使用された例もある。
このことから「同胞」は、地球における東スラブ系が住民の大半を占める国と地域に対しての認識表現であることがわかる。
長い宇宙移民の歴史を経てもなお、これらの国々とは、言語・文化に多くの類似性が認められており、そのことに親しみを感じることは無理からぬことだろう。
改めて言うまでもないが、同胞という言葉は「兄弟姉妹」のことであり、転じて同国民や同民族を指して用いられる。「同胞」と「兄弟」その言葉の意味に違いはないのである。
しかし、ヴェールヌイの一般大衆は、ベロガトーヴィチやロシジュアを「同胞」と表現しても「兄弟」と言うことは稀だ。
「兄弟」はガトーヴィチに限って使用されている傾向があり、そこには「同胞」と区別された特別な感情が反映されているようだ。単に親しみ込めているというわけではなく、その根本にはヴェールヌイ人の持つ鬱屈とした思いが見え隠れする。
本記事は、ヴェールヌイ人がガトーヴィチに対して特別な感情を形成するに至った歴史過程を整理し、諸要素を列挙しながら、これを紐解くことによって、今一度、社会主義共和国に生きる我々自身を見つめ直すものである。
ブルースター編集部
ヴェールヌイ人のメンタリティは、良くも悪くも、特異な社会主義制度を反映した社会生活の中で形作られる為、政治的観念の中で自己規定を強いられていると言えよう。
ヴェールヌイ社会主義共和国を建国し、唯一支配政党として十数年を過ごし、民主化後も絶対与党の地位を有するヴェールヌイ労働党による治世は、一言に、国家主義、単独主義の色濃い社会主義イデオロギーの、世界的優位性を誇示し続けることによって保たれていた。たしかに、先進国水準での完全自給経済構築を土台に、汚職の厳罰化、議会制度の透明化、政府主体の情報開示の推進で、既存社会主義が逃れる事ができなかった「統制が抑圧に転化すること」を幾分は回避しており、それまでフリューゲルに存在した社会主義国と一線を画していた。ただしこれらの功績は、その殆どがスヴィトラーナ政権時代のものである。スヴィトラーナ政権は、その後のいかなる政権と比べても、個人へ権力が集中した超トップダウン型であった。
それは、法規上はどうあれ、民主化以前のノルシュテインの権力をも上回るものだったと評される。国父ノルシュテインは「徳をもって人民を教化」し、その徳の原泉を、指導者と大衆の相互の信頼に求めた一方、スヴィトラーナにとって指導者の徳を示すということは、揺るぎない決断力と力の行使であった。
ノルシュテインは、自らに対する個人崇拝や神格化を嫌い、時のフリューゲルには存在しなかった永続性のある社会主義国の確立を夢見た。指導者個人の優位性ではなく、提唱した制度の将来性を、人民に確信させたかったのであり、その優位性と将来性は、スヴィトラーナの手によって証明された。
スヴィトラーナもまた、敬虔なノルシュテイン派であり、彼女の権力によって成された数々の成功は、彼女の意思によって、そのまま国家の思想と政治体制による成果に還元され続け、ノルシュテインの社会主義は「純粋社会主義」として、ノルシュテインまたはスヴィトラーナ本人に代わって「信仰」の対象になった。
しかし、全ての成果の原泉であり帰結先となった国家思想「純粋社会主義」は、制度としての生産統制に対し、民主的な正統性を与え、その利潤を人民の自由な生活様式の強化に注ぐという、循環システムの概念フローであって、それ以上でも以下でもない。経済の根本原理を、大衆が尊び続けるためには、経済的に成功し続けるほかない。そして、純粋社会主義がいかに優れた社会主義思想であったところで、実際に生産調整を行い、労働し、消費するのは人間である。
スヴィトラーナ政権が、純粋社会主義を証明する頃には、並行して「優れた制度を戴く国民国家」としての思想教育と、それに連なる専門化、精鋭化教育が実を結び、今日まで続く強固な官僚制度の土台が作られていた。スヴィトラーナの退陣後、600年代にかけて政治の力が衰退の一途をたどり、ついには経済調整に関心を示さなくなってからも、三世紀以上に渡って大きな破綻を来さなかったのは、純粋社会主義が優れていたというよりも、高度思想教育と官僚制度のもと、勤勉で従順な国民が、個々の役割を全うしたからに他ならない。
ヴェールヌイ人は、一貫した権威や意思さえあれば、極めて優れた集団性を発揮する人々なのである。ノルシュテインが指導者として優れていたのは、この国民性・民族性を看破し、巧みに利用した点にあったとも言えるだろう。
600年代の初頭には、政府によって全国調査「人民勤労/生活様式調査」(旧wiki)が実施されており、ここでもヴェールヌイ人の国民性が明らかにされている。
調査結果を要約すると、ヴェールヌイ人は「規則や法律を重んじ、規律を厳格に守ろうとするが、時に融通がきかない。自身が他人より秀でることを嫌う。従順かつ寛容的で、これらは他人を気遣う心と、理性的で落ち着いた振る舞いを保つことに貢献しているが、一方で主体性に欠ける」という。つまり優れた集団性の裏返しとして、個々の自律性が低いのである。
民族(俗)文化や宗教といったものは、個々の生活においては、純粋社会主義という概念フローよりも、身近で実態性があるものだろう。
これらが、民族主義や宗教権威として指導性を発揮しようとすれば、自律性がなく従順で集団性に優れるヴェールヌイ人は、ひとたまりもないのである。
620年以降、大きな破綻がなかったとはいえ、経済の衰退が刻々と進み、これを支えるべき政治力の低下も同時に発生していた。大スラーヴ主義の伝播は、まさにこの隙を突いていたのである。
大スラーヴ主義が共和国に与えた影響と、その顛末については957年12月の人民議会特別委員会の報告が詳しいので、ここで振り返ることはしない。
しかし、大スラーヴ主義の伝播は、先に述べた政治的観念の中でしか自己規定しえなかったヴェールヌイ人に、スラヴ民族という、秘められていた要素を思い出させることになったのは確かである。
そして、スラヴ民族としての自己規定が進むことは、同時に同胞への関心を喚起することにも繋がった。
この時代、それまで注目されていなかった言語学や民俗学、そして遺伝子学の分野でも、ヴェールヌイ人というコミュニティがいかにして成立したのか、言い換えればベルーサの起源を探る研究が盛んになった。
ベルーサの起源は、それまで「東スラヴ系に属する多民族の乗り合いでフリューゲル移民を敢行した船団に起源をもち、これが緩やかに同化したもの」(旧wiki)と説明されてきたに留まり、これは半ば神話のようなものだった。この神話における「緩やかに同化」の過程は「消極的な多文化主義(エスノセントリズムを否定しながらも、同化を恐れない立場)へと変質し、5世紀もの月日が経過する頃には、狭い民族主義的概念と地球における確執は、完全に一掃されていた」(旧wiki)とされ、それ以上の詳細はないものであった。
そんな中、遺伝子学の分野で、ある研究結果が発表される。
スラヴ人は、ハプログループR1a (Y染色体)が高頻度である特徴があることは従前から知られている。そしてフリューゲルのスラヴ人を計測比較したところ、ヴェールヌイ人(ベルーサ人)とガトーヴィチ人は同値の57.7%であることが確認されたのである。
(後の追加研究も含めた結果として、北ヴォルネスク人で59%、ロシジュア人で55.8%、南スラヴ系とされるセニオリス人(フルヴァツカ人)で6%であった)
Y染色体ハプログループ / ヴェールヌイ人とガトーヴィチ人(同一値)
R1a57.7%、I26.9%、R1b8%、E1b1b7.1%、N5.5%
この結果は、ヴェールヌイ人とガトーヴィチ人が、混血の形跡も含めてまったく同一であることを示していた。
(なおこれによって、ガトーヴィチが単一民族国家であることも同時に証明されている)
もちろん、ガトーヴィチ帝国(427年1月建国)とヴェールヌイ社会主義共和国(564年7月建国)は、どちらか一方からの移民によって成立した国ではない。
にも係わらず、ここまでの完全な一致を見たことは、両国の歴史家を騒然とさせることになった。

完全な同一民族であった両者が、その事を双方が認識しないままに、別の地域を版図として国を興し、数世紀を経過したことは、歴史上の謎のひとつである。
両地域の建国以前の歴史は、資料の残存数が少なく、その研究を困難にしているが、僅かに確認できる建国史だけでも、両者の類似性を確認することができる。
建国史における両者の類似性
・移民船団到着から、相当の期間を経た上で建国されていること
・到着時点から建国までに、他民族との混血機会がないこと
・建国以前には、村を単位としたコミュニティがあり、それらが緩やかに連帯していたこと
・建国に先立ち、地域統一をめぐる争いを経験していること
→ガトーヴィチでは、村々が地域の統一的王位をめぐり戦争が発生(王位戦争) 結果としてリース村が勝利(リーソフが王位に就き)し、帝国が成立した
→ヴェールヌイでは、ノルシュテイン(ヴェールヌイ組織)による地域内生産統合と、それに反対する村々の在地領主、そして在地領主間の争いが同時に行われ、結果としてヴェールヌイが勝利し、共和国が成立した
推測の域を出ないものの、ヴェールヌイとガトーヴィチに到着した我々の祖先は、元は同一の移民船団であった可能性が浮かび上がる。
混血形跡の一致は、建国史でその機会が双方なかった事からも、すなわちフリューゲル到着以前、おそらくは移民途上で混血機会を共有していた事を示している。
唯一確認できる大きな違いは「稲作文化」の有無で、ガトーヴィチについては大多数が、ヴェールヌイについては皆無である事を考えると、その違いにより区別され、到着地の違いに表れたのではないかと想像できる。
稲作文化の有無が、両国の体制的差異に?
両地域が経験した、地域統一をめぐる争いも、この稲作文化に焦点をあてることで、その性質が見えてくる。
ガトーヴィチにおいては、地域統一の動機が「外部の存在」であったのに対し、ヴェールヌイは「貧しさ」にあった。
ガトーヴィチ人の祖先がガトーヴィチに定住を決めたのは、それが稲作に適した土地であることを確信したからであり、王位戦争は対外的な権威を創出する為に行われた。
一方のヴェールヌイは、貧しさの解決策として地域統一が目指されたのであり、権力争いは副次的なものにすぎない。
同一民族である両者が、片や立憲君主制、片や社会主義共和制となった背景には、稲作文化の有無による祖先達の困窮の度合いがあったのかも知れないのだ。
さて、これ以上の建国以前の考察は歴史家に譲るとして、ヴェールヌイ人とガトーヴィチ人がまったくの同一民族であるという事実は、上記のような推測と共に、大いに関心が持たれるところとなった。
ヴェールヌイ人にとって「言葉が通じる同系の国」でしかなかったガトーヴィチ観は、これを機に徐々に変容することになる。
君帝という君主と伝統を戴き、世界一の工業国として栄え、政治・外交・文化(宗教)のあらゆる面で(賛否は山ほどあろうが)存在感を発揮しながら、ある種の奔放さを感じさせるガトーヴィチは、統制と慎ましさを美徳とする社会に生きる自分たちとの対比の中で「自分たちのもうひとつの可能性」を示唆し、時に「憧れ」であり、時に「反面教師」として、その存在を大きくしていった。
世界的に見れば、ガトーヴィチ人は奔放、ヴェールヌイ人は生真面目といったステレオタイプで評されることも少なくない。
しかし(少しメタ寄りの表現も含むが)国土に対する美意識、災害や建造の設定反映、文化交流や放送に対する興味と熱意、政治的立場に基づく時に頑固な姿勢(そして強硬に出たあと、実は小心で怯える点)など、両者の性質の類似は枚挙に暇がない。
ガトーヴィチ人に対する奔放のイメージは、基本的にその政治体制と外交政策のあり方から醸成されたものだ。
大スラーヴ主義や正教主義と国家の指標を替え、決定的な敗戦を経験しても、基幹となる君帝制を維持しつつ、大国として一定の地位を護っている。
つまりガトーヴィチ人も「一貫した権威や意思さえあれば、極めて優れた集団性を発揮」し、その一方で「個々の自律性が低い」のであり、この点もヴェールヌイ人と同質なのだ。
建国後、数世紀に及ぶ政治・社会制度の決定的な違いが、所作や得手不得手の違いとして表れてはいるものの、本質的要素で類似性を維持していることは、興味深い事実である。
ここまで、ヴェールヌイ人が、自らをスラヴ民族として自己規定することになった前提として、共和国の政治・社会的背景、国民性を振り返ると共に、現在まで影響を残すスラヴ問題の要因となったガトーヴィチが、完全同一民族であるという事実と、両者の本質的類似性について述べた。ヴェールヌイの大衆が、両国を「兄弟国」と表現していることは、同一民族であるという事実が広く認知されていることに加えて、これまで述べてきた類似性を、無意識的であれ感じていたからだろう。
970年代の今日、共和国は政治的にも経済的にも復興した。
国庫収入は歴史上最も高い数値を記録し、債権国として対外純資産を増やし、Funの保有高も世界最高になった。名目上の国民幸福度も、今や先進国で第一位だ。純粋社会主義という経済の循環フローを、信仰の対象にする為の前提を、ひとまずは取り戻すことができたのである。
(本紙は、私達が、そのことに細やかな誇りを持つことを否定するものではないが、本文でも述べたように、その危うさは指摘しておかなければならない)
一方のガトーヴィチは、紆余曲折を経て世界最大の債務国となり、資源や生産管理でも杜撰さが目立つ。国民幸福度は先進国最下位であり、直近の選挙では右傾化がさらに顕著となった。これらの点で、帝国は共和国の対極にある。
両国は、大スラーヴ主義、ヴォルネスク独立戦争、国家機能停止、813年戦争と、それぞれに盛衰を経験しつつも、基本的に先進国の一角を占め続けている。
そして今日に至るまで、明確に友好国であったことも、敵対国であったこともない。旧ソサエティを始めとした、複数国間の枠組みで言葉が交わされることこそあれ、二国間協議が実施されたこともない。ガトーヴィチとヴェールヌイは、基本的に「自ら外国に会談を持ちかける側」であるにも係わらずである。
勿論これは、時の国際環境と、両国の政治外交上の現実により、そうなっているに過ぎない。
誤解を恐れず言えば、ある一定の範囲内において、指導的地位を欲する点でも、両国の性向は一致しており、このことで世界の経済や軍事といったパワーバランスの中で、基本的立場を異にする不仲の兄弟なのだ。
まさしく「血は争えない」といったところだろう。
この兄弟観は、はじめは衰退するヴェールヌイにおいて発祥したものだが、近年ではガトーヴィチにおいても広まりつつある。国が苦境にある時、双方は最も近い隣の芝なのだ。
片方の成功は、同一民族としての誇りを感じさせる一方、嫉視することにもつながっている。
両者はその性質から、これからも盛衰を繰り返す。
時に憫笑し、時に哀れみ、時に手を差し伸べ、時に取り込もうとするだろう。
打算的な考えを超えて、兄弟愛を享受することは、もはや望むべくもない。
弊紙は、本記事において、両国友好又は警戒、ましてや民族の連帯を主張するものではない。
両国関係は、理性と現実に沿って展開されるべきであり、それが健康的な姿だ。
宇宙移民から10世紀を迎えようとしている人類は、いまだに自らを体制や民族、宗教といった壁によって区分しようとし、真の相互理解、種としての連帯の糸口を掴めずにいる。もしかしたらそれは、超越という概念や、AI統治であるのかもしれないが、それらが更に進化を重ね、また全人類が順応するには、少なくとも更に10世紀を要するだろう。
しかしそうした先でこそ、この兄弟は心から再会を喜び、分かち合うことができるのかもしれない。